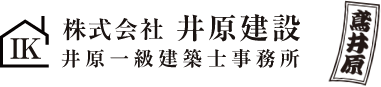建方とは、木造建築の場合には土台・柱・梁(はり)・小屋組を組み、最後に屋根上部に”棟”を架けることいい、”棟上げ”や”建前”とも呼ばれます。
初めての建方見学のため、会長に現場まで連れて行ってもらいました。
こちらのお宅は3階建てで、すでに3階部分の床板を張っているところでした。



3階床板を張り進めると、3階部分の柱や梁となる木材をクレーンで吊り上げて運びます。

クレーン操縦士さん、荷下ろしを調整する人、全体を見ながら両者の合図を中継する人と連携を図りながら、木材を上の階へ運びます。

3階部分の柱を立てていきます。

木造建築の設計図・建築現場では、最も基本となる基準線のことを”通り芯”と呼び、その表現には「いろはにほへと…」のいろは順と数字が使われています。
※写真の梁には「ろ5」と記されています。

柱を立てたら梁を架け、しっかりとはまるように上から掛矢(木槌)で叩きます。

一番上には屋根を支えるための骨組み(小屋組み)をつくります。
基礎工事からここまでの組立てが鳶の仕事で、ここからは大工さんにお任せします。
昔は、建方が無事に完了したことに感謝し、また、家が無事に完成することを祈願するために屋根の下でお神酒や神様にお供えした飲食物をいただく直会(なおらい)を行い、木遣り(きやり)を唄ったりしていたそうです。
※木遣、木遣りとは、労働歌の一つ、木遣り歌本来は作業唄だが、民謡や祭礼の唄として、各地に伝承されている。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
また、上階の四方の梁の上に半紙を置き、重ね餅をお供えする、その重ね餅は縁起物として、直会の最後に上から投げ、親戚や近所の人たちが受け取る、というならわしがあるそうです。
しかし、最近はそのようなことを行うところは少ないようです。
水回り・内装・外装・新築まで、住宅のお悩みならお任せください。
「玄関ドアの鍵交換」「電球交換」といったことから、「水回りや外壁のリフォーム」「新築工事」まで、様々な工事を請け負っております。
越谷市近辺につきましては現地調査やお見積りの費用は頂いておりませんので、お気軽にお問合わせください。